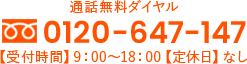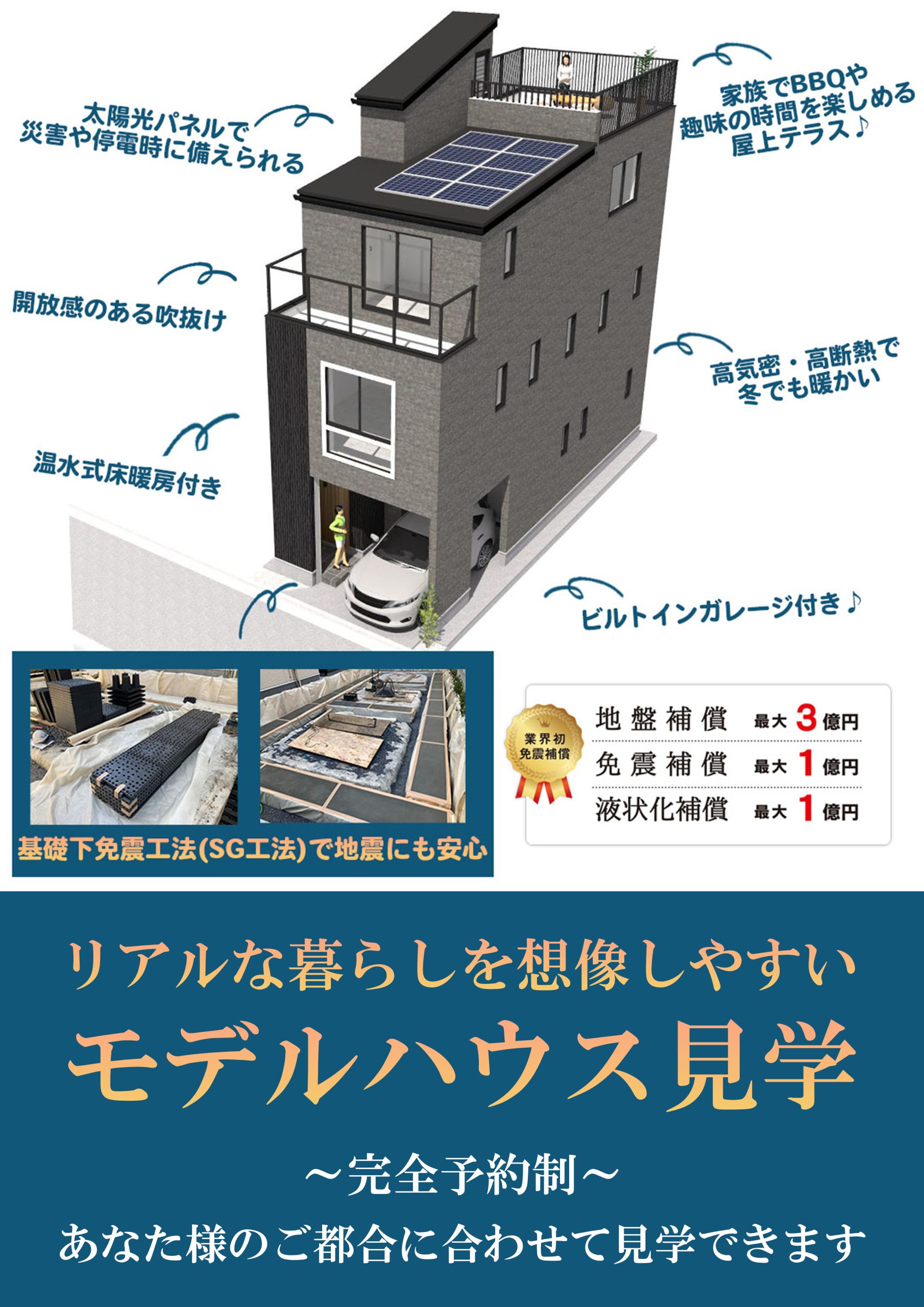大工の技術伝承が途絶えたとき
前回でお話ししたような、腕のいい大工の技術伝承が、日本で失われてしまった時期があります。
それが高度経済成長の時代、日本で家がどんどん増えていった時期です。
かつて、大工の社会は徒弟制度で、幼いころから親方の元に住み込んで奉公をしました。
最初は家事の手伝いをしたり、道具を運んだりといったところから始めて、
鉋のとぎ方やのこぎりの引き方を習い、徐々に板削りや穴堀りの仕方を習得し、
ほとんど一人前と見なされる頃に、ようやく敷居入れや天井張りなどを学びます。
その間は、衣食住の面倒は見てもらえましたが、賃金は出ず、小遣い程度でした。
奉公が明けてからも数年の間は、お礼奉公といって親方の元で変わらず仕事をし、
一人前の職人と認められたのはそのあとのこと。
職人は、こうして長い年月をかけて、みっちりと技術を叩き込まれていたのです。
しかし、高度経済成長の時代になると、職人の数が足りなくなるほど、
家づくりの需要が高まりました。
家がどんどん増えて、どんどん建てなければならない。
しかも、その時代は都会に出て、サラリーマンとして働くのが人気で、
職人のなり手も減ってしまっていました。
そうなると、「にわか職人」ですら重宝されます。
本来なら年季が明けるまで親方の元でみっちりと仕込まれるはずなのに、
その前に「こんなことやってられん」「もう家が建てられるだけの技術は身に付けた」
とばかりに独立してしまい、中途半端なまま、家づくりに携わる職人が増えていったのです。
きちんと技術を身に付けた上手い大工だと、ほぞ穴の寸法もピッタリで、
棟上げをしたときに、材木どうしがビシッとはまって気持ちがいいものです。
しかし、未熟な腕しかない大工だと、ほぞ穴と材木がピッタリはまらなかったりするのが
怖いため、穴も大きめに掘ったりしますし、下手をするとほぞ穴を掘る場所がずれていたりします。
こうなると、当然、家の強度も弱くなります。
ほぞ穴にピッタリ、ビチッと材木がはまっているのと、
穴がグズグズでグラグラしたり、傾いたりしているのと、
どちらが強いかはみなさんにもすぐおわかりいただけるでしょう。
また、現在であれば、家の強度を保つためにはどこに何本の柱が必要か、
などといったデータが出ていますが、当時は各職人の勘で建てられている部分もありました。
一流の腕を持った職人の技があっても、それはその職人集団の独自の技で、
広く伝承されるものではなかったのです。
そうなると、たとえばお客様から、
『こんなところに柱があると使い勝手が悪いから、この柱はどけて』
という要望が出たりしたときに、きちんとした科学的な根拠に基づいて、
その柱が必要なのかどうかを判断できないことになります。
腕のよい大工であれば、自身の経験に基づいて、まず間違いのない判断を下せるのですが、
未熟な大工になると、その判断がどうしても曖昧になってしまいます。
結果、お客様の要望を優先することになり、それによって、
強度が不十分になるケースも往々にしてあるわけです。
つまり、高度経済成長の時代に「増やせ、増やせ」といって建てられた家の中には、
こうした粗悪な家を含まれていたということです。
そんなわけで、世間的な評価としても「そこらの大工や工務店じゃダメや」
という風潮ができあがってしまったのです。
失敗しない家づくりブログその他のブログ記事